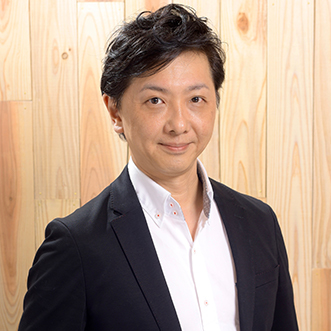頭痛の原因はもしかしてストレスかも…。
「市販薬で治る?」
「病院は何科に行けば良い?」
お医者さんに詳しく聞きました。
自分でできる対処法をはじめ、病気の可能性についても解説します。
監修者

荒牧内科
院長
荒牧 竜太郎先生
西田厚徳病院
平成10年 埼玉医科大学 卒業
平成10年 福岡大学病院 臨床研修
平成12年 福岡大学病院 呼吸器科入局
平成24年 荒牧内科開業
ストレスが原因で起こる頭痛
ストレスで頭痛が起こるワケを、原因別にご紹介します。
緊張型頭痛
精神的ストレス(精神的に緊張した状態が続く等)、身体的ストレス(パソコン・スマホの長時間使用、悪い姿勢等)が原因で筋肉が緊張状態になり、血流が悪くなって頭痛が起こると考えられています。
頭痛に加えて、倦怠感、肩こり、首筋のこり、眼精疲労等の症状が出現する場合があります。
片頭痛
ストレス、アルコール類、強い光、大きな音等も影響を与える場合があります。
生理や妊娠、更年期等、女性ホルモンのバランスの変化が原因で片頭痛があらわれることもあります。
ズキズキと脈打つような頭痛、吐き気、嘔吐等の症状が出現します。
群発頭痛
ひどい頭痛が1時間ほど続く状態が、1~2か月間ほぼ毎日群発するケースが多いようです。
その他にも、飲酒、気圧変化、睡眠不足、過労等も頭痛を起こす原因になる場合があります。
片頭痛との違いは?
片頭痛よりも激しい我慢できない程の頭痛(目の奥、こめかみ)や頭痛が生じている側の目の充血、涙が出やすい、鼻水が出る、鼻が詰まる等の症状が出現します。
メニエール病
日本には、4.5万~6万人ほど患者数がいます。
原因ははっきり解明されていませんが、ストレスが多く体調不良が続いている30〜50歳の女性に発症しやすいと考えられています。
ストレスによる頭痛に市販薬や漢方は効く?
ストレス性の頭痛は、市販薬や漢方薬の服用で頭痛症状が緩和される場合があります。
市販薬

<イブプロフェン・アスピリン主剤>
プロスタグランジン※生成を抑制し、痛み、炎症、熱を抑える
- イブ
- ノーシンピュア
- バファリン
- バイエルアスピリン 等
<アセトアミノフェン主剤>
中枢性作用により痛みや熱を抑えるが、抗炎症作用はほぼない
- セデス
- ノーシン
- タイレノール 等
※プロスタグランジン…ホルモンに似た生理活性物質の1つで、痛みや熱の原因物質となります。
頭痛の緩和が期待できる漢方薬
次の漢方薬を使用するのもおすすめです。
- 呉茱萸湯(ゴシュユトウ)
- 葛根湯(カッコントウ)
- 釣藤散(チョウトウサン)
薬が効かない場合の対処法
薬が効かないときは、次の方法を試してみましょう。
ツボ押し
ストレス頭痛の改善におすすめのツボをご紹介します。
緊張型頭痛緩和に有効とされるツボ
- 天柱:首の骨両側にある筋肉の外側部分にあるツボ
- 百会:頭頂部の鼻と両耳の延長線が交わる部分にあるツボ
- 風池:後頭部と耳後方の骨のくぼみ部分にあるツボ
片頭痛緩和に有効とされるツボ
- 合谷:親指と人差し指の骨が合流するところからやや人差し指側にあるツボ
- 崑崙:アキレス腱とくるぶし外側の間にあるツボ
- 足臨泣:足の薬指と小指の骨が合流するあたりにあるツボ
ストレッチ・マッサージ
ストレッチやマッサージで頭痛が改善されることがあります。
肩を下げるストレッチ
両肩を上にあげてからスッと落とします。
10~20回ほど繰り返し行いましょう。
首のストレッチ
左手を頭に乗せ、右肩の力を抜き、左へゆっくり首を倒します。
右側も同じように行い、5~10回ほど繰り返しましょう。
頭蓋骨のマッサージ
①両手の指を曲げて(グーの形)、小指と薬指の第二関節を耳の上に押すように当てます。
(指の位置を徐々に移動しながら一か所10秒くらいの間隔で押す)
②両手を広げて、小指球をこめかみ下に押し当てて、後ろ回しでぐるぐると10回程度マッサージしましょう。
食べ物・飲み物
次の栄養素を含む食べ物がおすすめです。
ビタミンB群(特にビタミンB2)を含む食べ物
- 緑黄色野菜
- 卵
- レバー
- 大豆
- 乳製品
- 鶏肉
マグネシウムを多く含む食べ物
- 納豆
- ほうれん草
- 米
- 味噌
- ひじき
- のり
- 魚介類
- 豆腐等
飲み物では、オーガニックの野菜や果物のジュースを飲むと良いでしょう。
旬の野菜や果物を使って手作りするのもおすすめです。
その他の対処法
- 頭痛が起きた場合は、できるだけ暗くて静かな場所で安静にしましょう。
- 緊張型頭痛の場合は、お風呂等に入り温めると症状が緩和する場合があります。
- 片頭痛の場合は、温めずに冷やすことで症状が緩和する場合があります。
- スマホやゲームを長時間使用せず、時間を決めて行うようにしましょう。
- 長時間同じ姿勢で過ごさないようにしましょう。(15~30分に1回ほど軽く体を動かす等)
記事の続きは、「Medicalook」でお読みいただけます。
記事は、健康検定協会から提供されています。